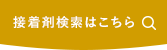なぜ木材か?
4.木材は人にやさしい
(1)適度な湿度に保つ
木材は、空気中の湿度が高いときには水分を吸収し、湿度が低いときには水分を放出するという調湿作用をもっています。このため、木材を建物の内装などにたくさん使うと、部屋の中の湿度の変動は小さくなります。
(2)断熱性能が高い
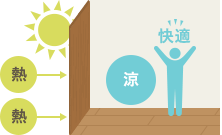
木材は無数の細胞からなり、そのひとつひとつに熱を伝えにくい空気を含んでいるため、コンクリートなどに比べ高い断熱性をもっています。
木材、ビニールタイル、コンクリートを床材にして、足の甲の皮膚の温度変化を測定すると、コンクリートがもっとも足が冷え、木材がもっとも冷えなかったという結果が得られています。
![]()

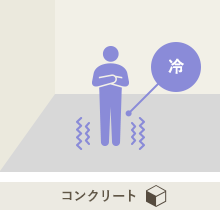
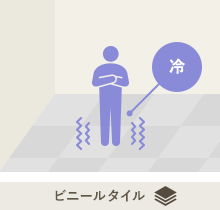
![]()
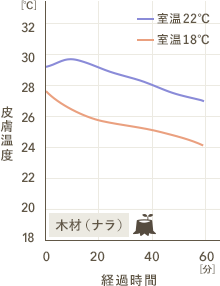
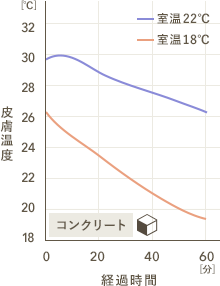
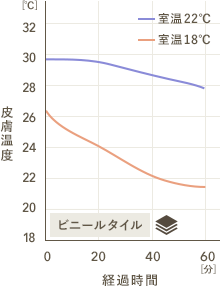
資料:山本孝 他「木材工業」Vol.22-1.P24,1967
農林水産省 林野庁
(3)衝撃吸収能力が高い
木材はパイプ状の細胞が柔軟に変形してクッションのような役目をするので、例えば大理石に比べて2~3倍の衝撃吸収能力があります。
このため、床や壁に木材を上手に使用することは、転倒などでの怪我の防止につながります。
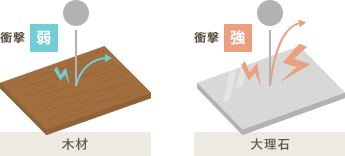
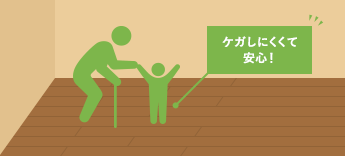
(4)目にやさしい
木材は紫外線をよく吸収するため、木材から反射する光にはほとんど紫外線は含まれません。
紫外線の反射が少なければ、目に与える刺激も小さくなることから、木材は目にやさしい材料であると言えます。
(5)音をまろやかにする
木材は音を適度に吸収してまろやかにし、心地よく感じる範囲に調整してくれます。
木材を使った 部屋は「音がいつまでも響かず適度に反射する」ので音が聞きやすいといわれています。
(6)木材は健康に良い
木材は人の生理面や心理面に良い影響を与えることが知られています。
例えば特別養護老人ホームでの調査によると、木材を多く使用している施設では、インフルエンザにかかったり転んで骨折をしたりする入居者が少ないという結果が出ています。
マウスを使った実験では、木製の飼育箱で生活するマウスの方が金属やコンクリートの飼育箱より生存率が高い結果が出ています。体重の変化を見ても同様です。
![]()
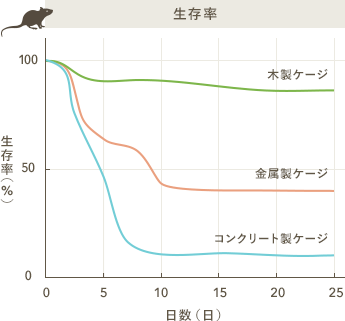
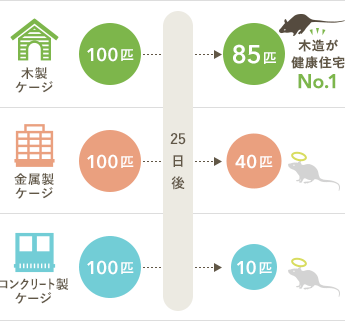
農林水産庁 林野庁
資料:伊藤他、静岡大学農学部(1987年)
ある小学校で、木製の机を椅子を導入したところ、子供達が物事に熱心になった、あくびがあまりでなくなったといった「良い傾向」となったと回答した教師が多かったという調査結果も出ています。
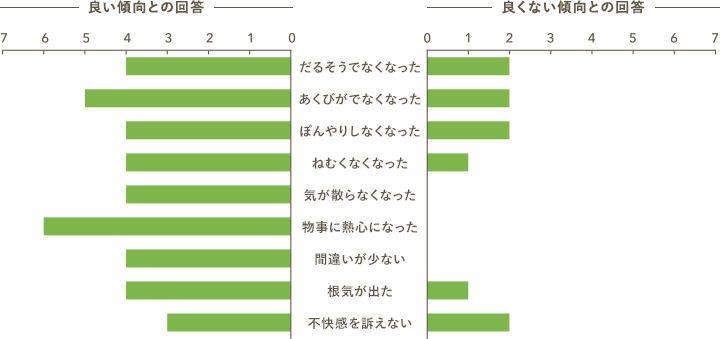
出典:小川正光ら「木製の机・椅子が教育効果に及ぼす」(愛知教育大学家政学教室研究紀要、平成11年3月)より作成
※小学校15校の6年生32クラス(児童数1,056人)の教師32人を対象に、教室の机と椅子をスチール製から木製に切り替えた前後の児童の様子の変化を、教師より回答を受けたもの。
※木製の机・椅子を導入した後、教師から見て、該当する症状の児童数が増えた場合を「良い傾向」とし、減った場合を「良くない傾向」として、回答した教師の数。
農林水産庁 林野庁
5.木は火に強い


アルミニウムと鉄と木材の加熱による強度低下試験を行なったところ、アルミニウムは400℃になると強度が80%ダウン、鉄は550℃を超えると50%ダウン。木は550℃で5%ダウン、800℃になっても40%しか低下しませんでした。
この実験データから分かるとおり、木材は火に弱いといわれていましたが、木材は表面が燃えても強度が保たれることが実証されました。
木は酸素の供給がなければ燃えることができません。木は表面から燃えていきますが、それは表面からしか酸素の供給がなされず、しばらくすると表面に炭化層ができ、この炭化層が熱を伝えにくくする作用があるため、燃え方が遅くなっていきます。
建築物として考えた時、素材と熱の関係性は重要です。
木は燃えますが、熱という 観点でみると木はアルミニウムや鉄よりも強いのです。
(2)木材が強い理由
鉄やコンクリートはとても強い素材ですが、共通して言えることは重いことです。
一般的に重い素材ほど強い素材と言えます。
では、同じ重さに対する強さはどうなのでしょうか?
引っ張り実験で木材は鉄の4.4倍、コンクリートの225倍の強さがあります。
圧縮実験では木材は鉄の2.1倍、コンクリートの9.5倍の強さがあります。
曲げ実験で木材は鉄の15.4倍、コンクリートの400倍の強さがあります。
つまり木材は軽い割りには他の材料よりも圧倒的に強い材料で、言い換えると、より少ない材料で強いものをつくることができるのです。
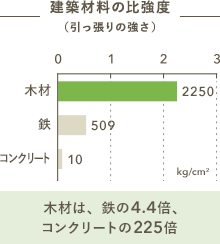
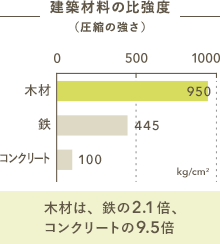
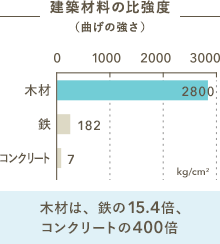
財団法人日本木材備蓄機構、社団法人日本林業技術協会「木をいかす」
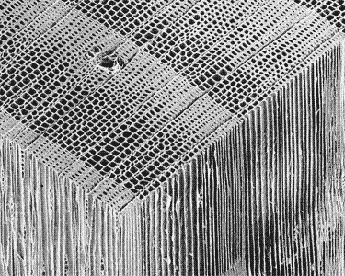
木材が軽いのに強い理由は、木材が中空のパイプのような細胞が無数に集まって出来たハニカム構造だからです。
はちの巣や、飛行機の翼の断面、段ボール紙の断面もハニカム構造に成っています。木材は軽くて強い自然素材なのです。
参考文献・出典 財団法人日本木材備蓄機構、社団法人日本林業技術協会「木をいかす」
参考:森林・林業学習館
6.木材の利用用途
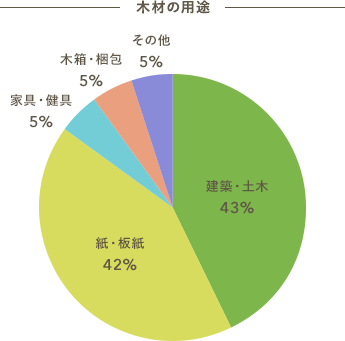
参考資料・出典
日本の森を育てる円卓会議 提言書「木づかいのススメ」
(財)日本木材総合情報センター「企業セミナー・木づかいのススメ」
世界で生産される木材のうち、約52.5%は薪炭材として使われ、その約半数は開発途上地域で生産されています。残りの約47.5%は建築や紙の材料など産業用に利用されています。
日本の木材用途をみると、建築・土木や家具・建具、木箱など、いわゆる木材としての利用を合計すると53%となり、半分以上を占めています。これらは、日本古来からの木材の用途として、ほとんど変わっていません。
従来は約47%を薪炭材に使用していましたが、現在は、紙・板紙の原材料としての利用が42%程度となっており、現代社会ならではの木材の利用方法と言えるでしょう。
参考:森林・林業学習館
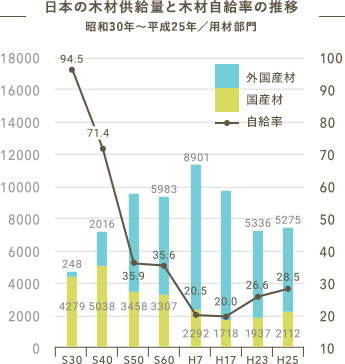
林野庁 木材需給表 より
日本の木材需給量をみると平成25年現在、7,387万㎥で自給率は約28.5%です。
自給率の推移をみると昭和30年の94.5%をピークとし、平成10年代に最も低くなり以降徐々に自給率が増え続けて今日に至っています。
京都議定書の温室効果ガス削減政策への取り組みもあり、木材の利用見直し、木材の良さが再確認され今後の新たな木材利用についても協議されています。
森林・林業白書(平成26年版より)
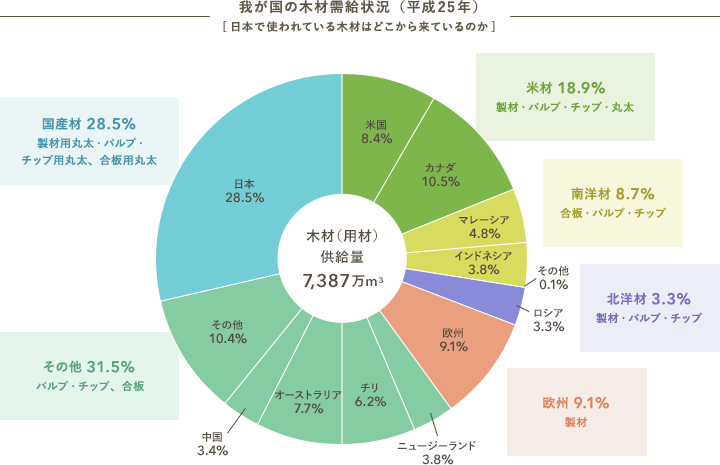
林野庁 森林・林業白書(平成26年版)より