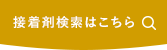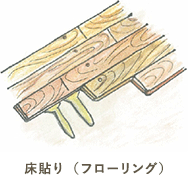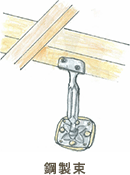接着剤の種類・分類
目次
Ⅰ. 水性系接着剤
- ユリア樹脂系接着剤
- メラミン樹脂系接着剤
- フェノール樹脂系接着剤
- レゾルシノール樹脂系接着剤
- 水性高分子-イソシアネート系接着剤
- 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤
Ⅱ. 溶剤系接着剤
- クロロプレンゴム(CR)系接着剤
Ⅲ. 化学反応系接着剤
- エポキシ樹脂系接着剤
- ウレタン樹脂系接着剤
- 変成シリコーン系接着剤
Ⅳ. ホットメルト系接着剤
水性系接着剤
ユリア樹脂系接着剤
尿素(ユリア)とホルマリンを主原料とする接着剤です。
常温接着用(濃縮型)と加熱接着用(未濃縮型)があります。
一般的に硬化剤として塩化アンモニウムや酸が用いられ、粘度調整と増量、接着後の接着層の老化防止を目的として小麦粉を加えたり、粘度調整に水を加えたりして使用します。
| 用途 | 合板、パーティクルボード、中密度繊維板(MDF)等 |
|---|---|
| 代表製品 | |
| 用途例 | 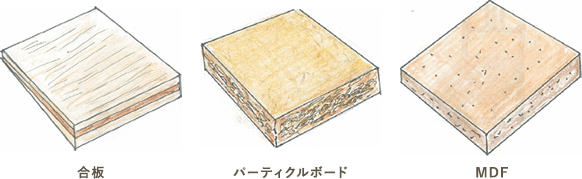 |
メラミン樹脂系接着剤
メラミンとホルマリンを主原料とする接着剤です。
使用方法はユリア樹脂系接着剤とほぼ同じですが、常温硬化が難しいので加熱接着を行います。
ユリア樹脂系接着剤と比較して耐水性、耐熱性、耐老化性に優れています。保存性が悪いことと高価であることから、尿素とメラミンとホルマリンを組み合わせる場合が多いです。
| 用途 | 合板、集成材、単板積層材(LVL)、パーティクルボード、中密度繊維板(MDF)、等 |
|---|---|
| 代表製品 | |
| 用途例 | 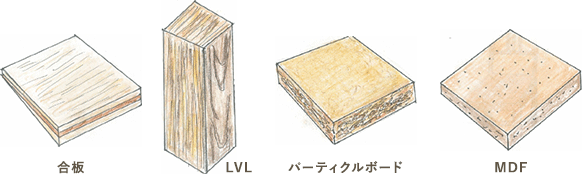 |
フェノール樹脂系接着剤
フェノールとホルマリンを主原料とする接着剤です。
常温接着用と加熱接着用があります。
使用時には充填剤(クルミ粉や木粉等)や、増量剤(小麦粉、炭酸カルシウム等)、水を混合して所定の粘度に調整します。
ユリア樹脂系接着剤やメラミン樹脂系接着剤と比較して加熱温度や時間が長く必要なので「硬化促進剤」を混合する場合もあります。
また、ユリア樹脂系接着剤やメラミン樹脂系接着剤と比較して耐水性、耐熱性に優れ、フェノール樹脂系接着剤で接着した合板は、JAS構造用合板の規格において、「特類」または「1類」の接着性能を示します。
一方接着剤が赤褐色のため、接着層は赤褐色となってしまいます。
| 用途 | 合板、単板積層材(LVL)、パーティクルボード、一般木工、等 |
|---|---|
| 代表製品 | |
| 用途例 | 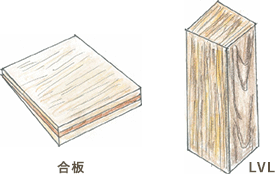 |
レゾルシノール樹脂系接着剤
フェノールと分子構造が類似したレゾルシノールとホルマリンを主原料とする接着剤。
フェノールに比べて硬化速度が速く、常温硬化が可能。
フェノール樹脂系接着剤よりもさらに耐水性、耐久性に優れる。
| 用途 | 構造用集成材、木造船舶などの耐水性・耐久性が強く求められる材料、等 |
|---|---|
| 代表製品 | |
| 用途例 | 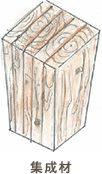 |
水性高分子-イソシアネート系接着剤
開発当初は「水性ビニルウレタン」と呼ばれたが現在はJISにより「水性高分子-イソシアネート系接着剤」と称されます。水溶性樹脂、合成樹脂エマルジョン、無機充填剤等を成分とする「主剤」と、イソシアネート化合物(MDI系)またはそのプレポリマーを主成分とした「架橋剤」とを組み合わせて使用します。
一般的に主剤/架橋剤=100/5~20の割合で混合して使用されます。
耐水性、耐熱性が高く構造用集成材にも使用されるが、木工用途以外では木質材~プラスチック、無機材等の複合材の接着にも使用されます。
| 用途 | 構造用集成材、耐力パネル、家具、一般木工、等 |
|---|---|
| 代表製品 | |
| 用途例 | 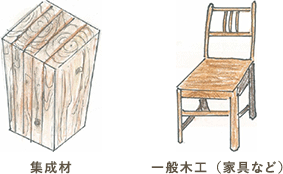 |
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤
溶媒(成分を溶かしているもの。エマルジョンでは「水」)を蒸発するだけで接着可能なため使いやすいです。
また分解による老化性が少ないです。
しかし一般的な酢酸ビニル樹脂系は耐熱性、耐水性、耐溶剤性が不足するため、これらの欠点を改良する工夫も行われています。(「変性」として一般酢酸ビニル樹脂と区別することがあります)
| 用途 | 木工、紙工、他多用途 |
|---|---|
| 代表製品 | |
| 用途例 | 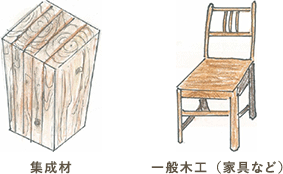 |
溶剤系接着剤
クロロプレンゴム系接着剤
クロロプレンゴムを主成分として溶剤に溶解した接着剤です。
数多くの被着材(接着されるもの)に対して良好な接着性を示し、コンタクト形接着剤※として有名です。
※コンタクト接着:被着材の両面に塗布し、溶剤を乾燥させて貼り合わせて、直ちに充分な強度を得る接着。初期接着性に優れています。
また耐劣化性、耐酸性、耐アルカリ性が良い反面、可塑剤の影響を受けやすいため可塑剤が多く含まれる軟質ビニルなどの接着には向きません。
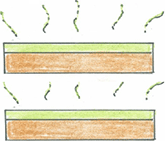
被着材それぞれに塗布して一定時間乾燥

張り合わせ
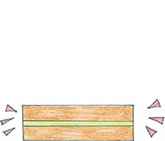
完了
| 用途 | コンタクト接着(木工、パネル、金属等多様)、等 |
|---|---|
| 代表製品 |
|
化学反応系接着剤
エポキシ樹脂系接着剤
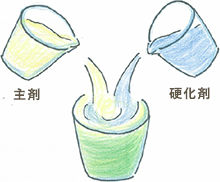
エポキシ樹脂の定義は、1分子中に2個以上のエポキシ基(オキシラン環)を有し、適当な硬化剤との反応によって3次元化した硬化物を与える化合物の総称です。
強度と耐久性を必要とする金属の接着に使用される場合が多いです。
主剤と硬化剤の混合比に正確さが求められます。
また硬化は化学反応を伴うので硬化の際の温度と硬化時間には密接な関係にあります。
低温では反応が進みにくいため冬場の使用の際には硬化温度を管理する必要があります。
硬化剤のアミン系化合物による皮膚刺激性だけでなく主剤のエポキシ樹脂自身の感作性(アレルギー性)も認められています。そのため使用時には適切な保護具の着用や換気が必要で、人体に付着した時は製品の注意書に従って直ちに対応する必要があります。
| 用途 | 金属、木工、パネル、コンクリート、等 |
|---|---|
| 代表製品 |
ウレタン樹脂系接着剤
イソシアネート系原料、ポリエーテル・ポリエステル系原料を主成分とした接着剤です。
1液タイプは水分と反応して硬化するものが多く、2液タイプはポリオール成分とイソシアネート成分を反応させます。
プラスチック、金属、木材、無機材料などの広範囲の用途に利用されます。一般的にエポキシ樹脂系接着剤と比較すると、金属接着性や熱劣化特性が劣りますが、樹脂設計により耐熱性、密着性を改善することが可能です。
| 用途 |
床、根太、鋼製束、タイル、木工(建材パネル) FRP浄化槽、プレハブ外壁コーナー部、等 |
|---|---|
| 代表製品 | |
| 用途例 |
|
変成シリコーン系接着剤
シーリング材として実績のある変成シリコーンを主成分とした接着剤であり、水分と反応して硬化します。
変成シリコーン系接着剤は硬化物が伸びたり復元したりするため、弾性接着剤とも呼ばれます。そのため引張りせん断接着強さは低いが、耐衝撃性や剝離接着強さに優れています。
また同様に湿気が反応に関与するウレタン樹脂系接着剤のような発泡はありません。
一方、接着層が弾性であるためクリープ(接着接合部に応力が加わったときに生じるひずみが時間と共に変化すること)に弱いだけでなく、耐熱性に課題があります。
| 用途 | 床、根太、鋼製束、木工(建材パネル)、等 |
|---|---|
| 代表製品 | |
| 用途例 |
|
ホットメルト系接着剤
ホットメルト形接着剤
JISで「溶融状態で塗布し、冷えると固まって接着する接着剤」と定義されているように、熱で溶かして液状にし、冷やし固める接着剤です。
無溶剤で冷却固化により瞬時に接着が完了するという高速接着性を活かした用途で活躍しています。
塗布後に熱による再溶融も可能であるため、材料表面にコーティングした後に加熱接着ができます。
しかし言いかえれば耐熱性に劣るということでもあります。
また熱に敏感な材料に対しては変形や変質などの注意が必要です。
さらに使用時にアプリケーター(加熱及び塗布機)が必要となります。
★ホットメルト系接着剤は湿気で硬化する性質を付与し、耐熱性、耐クリープ性、耐溶剤性などを改良した「反応性ホットメルト形接着剤」もあります。反応性ホットメルト形接着剤は通常のホットメルトと異なるため、硬化後に再溶融が困難であるだけでなく、保存時に湿気と触れないような注意が必要です。
なお冷却による「固化」と水分との化学反応による「硬化」は区別しています。
| 用途 | 製本、包装、衛生品、自動車、電気、木工、等 |
|---|---|
| 代表製品 | |
| 用途例 | 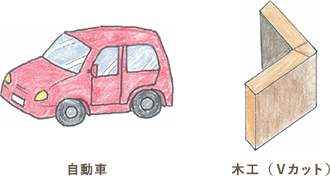 |